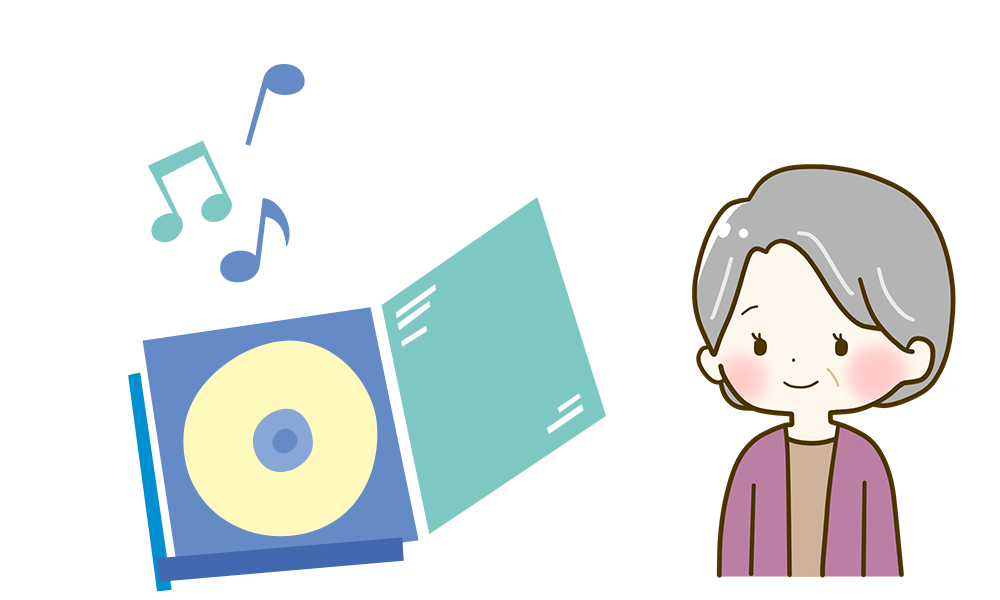
CDの貸し出しサービスをはじめた最初のころのはなしです。
受付に80代くらいの初老の女性がみえて「すみませんが、流浪の民という題名の曲がありますか」とのこと。さっそく検索してみるがヒットせず。もう少し詳しく話を聞くと、どうやら合唱曲らしいので棚を探してみることに…するとウィーン少年合唱団のCDの「野ばら~美しき青きドナウ」1990BMGビクターのなかにあったので女性に手渡すとすごく喜ばれて「死ぬまでにもう一度聞きたかった」とのことでした。
だけど、なんで検索で『所蔵なし』となったんだろうか?

理由は明白でした。図書とは違いCDのマーク(書誌データ)は当初、曲目は5曲までしかはいっていなかったのです。せっかく資料があるのに提供できないということのないようにすべてのCDの6曲目以降を手入力することにしました。CDは曲目なら全曲に対して歌手名、演奏者、作曲者、指揮者などの情報がないと資料としての意味がない。そのほかに、ジャンル別に分類される必要性があるが、図書のようにNDCで分類されていない。これに関しては各館、独自の音楽分類にしていると思います。限られた資料費の中から購入し、マ-ク代や装備代を捻出しなくてはならない。さらに、ケースが壊れればケースの修理代。盤に傷がつけば研磨代当館では、のちにコーティングもしているのでそれにかかる費用などなど…。
なので、CDを提供するにはたくさんの手間とお金がかかるのです。

