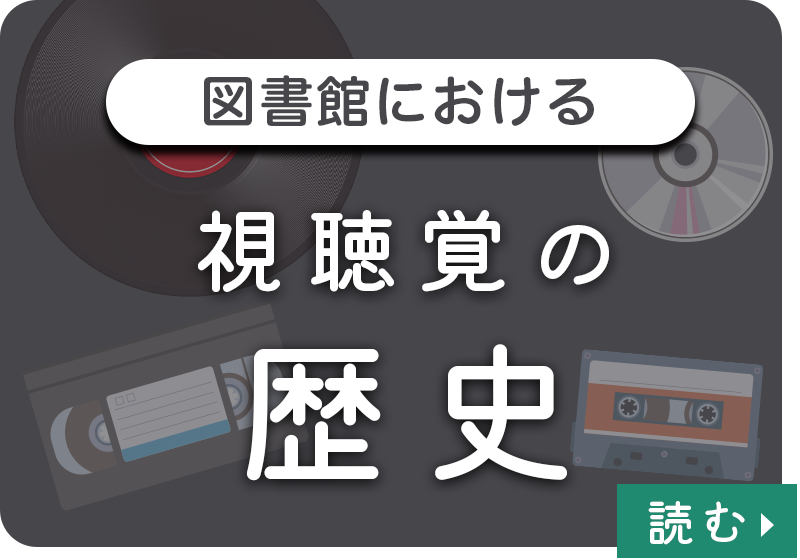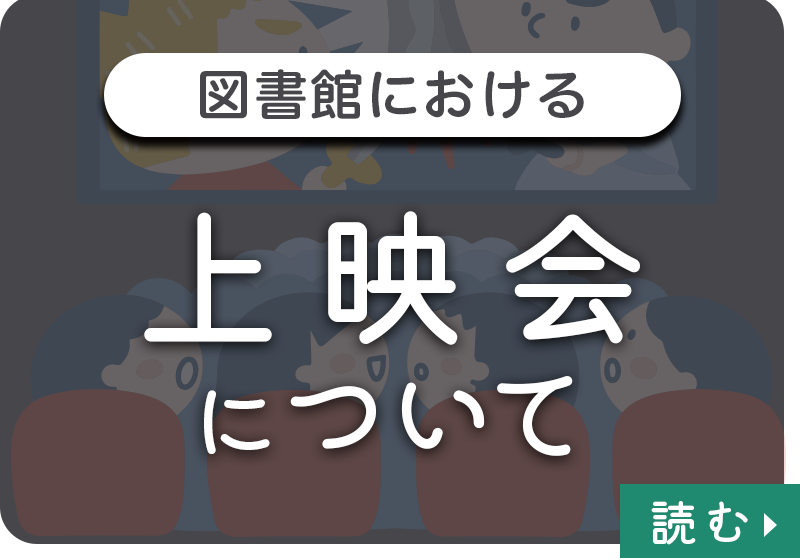【Q&Aコーナー】視聴覚の歴史
図書館における視聴覚の歴史
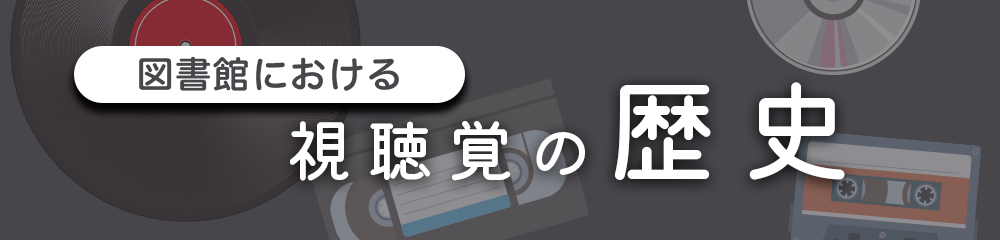
図書館における視聴覚の歴史 ①
日本では1950年に図書館法が制定され、視聴覚資料はその図書館法第三条(図書館奉仕)に明記されています。そこで取り扱われる資料の内容は「レコード」「カセットテープ」から「CD」、「16ミリフィルム」「ビデオ」からや「LD」「DVD」「CD-ROM」へと時代において変化しています。
図書館における視聴覚の歴史 ②
映像資料について
全国の図書館に著作権処理済ビデオを図書館に頒布する事業は1988年10月、山梨県石和町立図書館で「日図協ルート」として始まりました。洋画を中心としたメーカーと邦画を中心としたメーカー(日本ビデオ協会ルート)がありました。
図書館における視聴覚の歴史 ③
1998年5月、公益社団法人日本図書館協会(以下日本図書館協会と略す)に映像事業部が誕生しました。この頃には図書館に著作権処理済ビデオを頒布する事業として全国では1,800館を超えました。しかし図書に比べて歴史の浅いビデオ等に関しては、使いやすいMARCや装備の問題、資料の収集方針や選書ツール、予算や人の確保などが懸念されていました。ほとんどの図書館では兼務職員でした。
図書館における視聴覚の歴史 ④
1999年2月東京にある日本図書館協会にて第1回JL A視聴覚資料研究会が開催される。
この年より視聴覚資料の研究会として年2回のペースで行われるようになりました。この研究会はすでに視聴覚資料を扱っている図書館やこれから導入しようとする図書館にとってはたいへん参考になるとともに各図書館や各担当者との情報共有や情報交換、問題提起の場としても開催されました。その内容は「図書館と映像資料」の表題で冊子が作成され各図書館にて配布されました。
図書館における視聴覚の歴史 ⑤
2000年をむかえるとaudio-visualの世界はPlayStation2をはじめとしたゲーム機器類やDVDメディア、デジタル放送化などメディアの変化が著しく日進月歩しております。このような変化の中でパソコンの普及により、CD -ROMソフトの普及が目覚しく利用も増加しております。しかし、CD-ROMソフトは著作権処理が難しく図書館で貸し出せるものはまだ少なかったのですが日本図書館協会でIT時代に対応して積極的に取り扱うことになりました。 そして全国に先駆けて群馬県の高崎市立図書館で著作権処理済のCD-ROMをコーナーを設けてWindows版、Macintosh版、hybrid版の3つの形態の資料の貸出をはじめました。
図書館における視聴覚の歴史 ⑥
公共図書館の視聴覚資料については、1986年に大学、短大、高専などを含めて所蔵状況と利用についての調査報告「著作権法改正問題にかかわる図書館資料の利用」に関する調査書(1986年3月)が日本図書館協会から出されている。
しかし、この報告書からは所蔵と利用についての数値が得られるのみで、視聴覚サービスが当面している全体的な問題を把握することはできない。とある。
日本図書館協会が毎年実施している「日本の図書館」というのがあるのはご存じのことでしょう。1993年に実施した際に付帯調査として「公共図書館における視聴覚資料の収集と利用に関する調査」なるものは、質問項目ごとの集計を出し、公共図書館における視聴覚サービスの実態を浮き彫りにするために、若干の分析を加えた報告書である。当時としては、全国的な視野にたった視聴覚サービスの現状を知る資料が無かったことを考え、総合的な実態把握を目的に全体像に迫ろうと実施した。
この調査集計冊子が当時としては全国で最初であろうし、この報告書を執筆されたのは日本図書館協会著作権問題委員会・ビデオ専門委員会委員の竹内紀吉氏である。
図書館における視聴覚の歴史 ⑦
図書館の歴史⑥で紹介した「公共図書館における視聴覚資料の収集と利用に関する調査」報告書から約三年が経過した1997年3月には「図書館における視聴覚資料の収集と利用に関する実態調査」報告書が全国の公共図書館に配布されている。
この三年間に図書館における視聴覚資料の収集が活発となり、各図書館においても従来の書籍のサービスから、新しい視聴覚資料の提供が利用者サービスの中で一定の比重が占めるようになってきているが、それとともに、ビデオソフトによる上映会を中心とした著作権にかかわる問題が数多くおきている。
そこでビデオ上映会の実施を含めた視聴覚資料全般にわたってその利用実態を把握するための調査を行い、この調査報告書を作成した。
この作成には日本図書館協会著作権問題委員会・ビデオ専門委会委員長の大口欣一氏をはじめとする第25期ビデオ専門委員が携わった。
私もここで参加しお手伝いをすることになるのだが、この頃より山梨の小林是綱氏や千葉の竹内紀吉氏、埼玉の大澤正雄氏には特によくしていただいた。
当時は、若輩者ながら、このような方たちとご一緒させて頂くことで色々な事を教えていただいた。
図書館における視聴覚の歴史 ⑧
1998年5月より日本図書館協会に映像事業部が誕生したことは③で書きましたが、それ以前のことを伺う機会がございましたので少し触れておきたいと思います。
映像事業部のスタッフというか担当している職員は、前身のエイ・ブイ・システム・サービス株式会社(以後AVSS)1986年設立の社員さんたちでした。
1985年のプラザ合意(先進5か国でドル高是正のために各国が協調介入を行うことで合意)のあと、円高が進み輸出企業が振るわず、日銀は円高不況から脱するため、金利を下げて金融緩和をした。低金利下で、企業や個人は融資を受け、不動産や株を買いあさり加熱した結果、日銀は1989年に金利を上げて金融引き締めに転換。1990年に不動産融資の総量規制を実施して、不動産融資を抑制した結果、1991年~1993年にバブルが崩壊し公共事業は税収が増収した数年後に活発に…
丁度、バブルのお陰で増収した市町村では、図書館等公共施設が競争して新築や改築されていていました。あの時代の図書館を振り返ると音楽資料には歴史があるけど映像資料は殆ど…
図書館協会や一般市場への販売権を持つ販売業者に、映像資料を著作権法に基ずく価格はあまりにも高いので市場価格で入手できないかとの依頼がありました。そこで立ち上げたのが、当時、米CBSのレコード部門に在籍中だった野﨑達也氏(AVSS社長)が、同僚の方々や、業界の知人たちとの繋がりで、著作権者であるハリウッドの映画製作会社の社長や役員と直接、話をして許諾を得られたのです。
②で書いた山梨県の石和図書館で、自動貸出返却機をNTTデータと結び、毎月、貸出、返却の利用状況と石和町の電気店でのビデオデッキの動きやレコード店や本屋にビデオが置かれたりビデオショップが新規にできたりもしました。
男性社員をひとりつけて、1ケ月毎に1年間の状況を日米の業者に報告した結果、賛同が得られ全国展開したのです。
石和町は山に囲まれ、電波の制約もあり、手軽に映像に触れる機会が少なかったことも功を奏したかもしれませんし、石和町立図書館の小林是綱館長の熱意がけん引したことは確かである。
私も野﨑社長と奥様のマサヨさん(AVSSでは業務全般と仕事ネームは横見マサヨさん)と一緒に石和へ行き、小林館長にお会いしたことを昨日のことのように覚えております。
次々と色んなカタチで色んな映像が洪水のように押し寄せてくる今日(ネットや配信サービス)とは違い…映画館でハリウッド映画の迫力に興奮し、銀幕のスターに憧れたり、学生時代に感動した場面を何度も巻き戻しひとりで、のんびりとゆっくり楽しんだり、あるいは図書館で借りたビデオで夕刻のひと時を家族団らんのニューメディアとして…そんな時代だったから…
Windows95に時代を変えられてしまった今日。図書館に映像資料が導入されて約40年ちかくになりますが図書館にしかできないことが必ずあると思います。
PS.つい先日(6月下旬)AVSSの野﨑マサヨさんとお電話でお話をする機会があり、とてもお元気で、当時のことを懐かしく思いながら楽しかった思い出を色々と語ってくださりました。
図書館における視聴覚の歴史 ⑨
「図書館における視聴覚資料の歴史④」で紹介した「図書館と映像資料」の冊子はNo.1からNo.15まであり当時の視聴覚の問題点などについて大変参考になる。
現在、漠然とした視聴覚サービスをおこなっているのなら是非とも一読の価値ありです。(一部省略)
第1回JLA視聴覚資料研究会
1999年2月3日 日本図書館協会
①「映像資料と著作権-ビデオ問題の交渉経過」
(日図協著作権問題委員会・ビデオ専門委員会委員長)
②「図書館における映像資料の収集と活用」
(元浦安市立図書館館長・千葉経済大学短大部教授)
③「DVDの図書館への提供についての考え方」
(㈱)ソニーピクチャーズエンターテインメント取締役)
第2回JLA視聴覚資料研究会
1999年10月1日 岐阜県立図書館
「図書館における視聴覚サービスの実際」
(高崎市立図書館視聴覚係主任司書)
「視聴覚資料と著作権」
(日図協著作権問題委員会・ビデオ専門委員会委員長)
第3回JLA視聴覚資料研究会
2000年2月1日 日本図書館協会
①「映像資料のMARKについて」
(日本図書館協会専門員、前国立国会図書館専門調査員)
②「デジタル&ネットワーク時代の図書館と著作権」
(日本図書館協会常務理事・著作権問題委員会委員長、青山学院女子短期大学教授・図書館長)
③「DVD作品の図書館等への提供についての現状報告」
(日本図書館協会映像事業部)
第4回JLA視聴覚資料研究会
2000年9月5日 福岡市総合図書館
「視聴覚資料と著作権」
(青山学院女子短期大学教授)
①「伊万里市民図書館における視聴覚サービスについて」
(伊万里市民図書館館長)
②「瀬高町立図書館における視聴覚資料について-選択収集からサービスまで」
(瀬高町立図書館館長)
第5回JLA視聴覚資料研究会
2001年9月5日 日本図書館協会
①「図書館におけるビデオ等視聴覚資料について」
(日本図書館協会著作権問題委員会・ビデオ専門委員長)
「宮城県図書館における視聴覚サービスの現状と課題」
(宮城県図書館利用サービス班視聴覚資料担当主任主査)
②「図書館における映像資料の機能的な取扱について」
(㈱M.M.C代表取締役)
第6回JLA視聴覚資料研究会
2002年2月19日 日本図書館協会
「図書館におけるビデオ上映会開催について」
「図書館における視聴覚しりょうのメンテナンスについて」
第7回JLA視聴覚資料研究会
2003年2月14日 日本図書館協会
「図書館におけるビデオ上映について」
★文化審議会著作権分科会情報小委員会での「図書館等における著作物等の利用に関する検討」について
(日本図書館協会 前事務局長)
★「合意事項」に基づいた図書館での上映について
(日本図書館協会ビデオ専門委員)
第8回JLA視聴覚資料研究会
2003年9月25日 香川県立図書館
★「図書館と著作権問題~最近の上映問題の動向について」
(戸板女子短期大学教授・日図協理事)
★「図書館における映像資料についての現状報告~アンケートの集計に見る映像資料の現状」
(日本図書館協会 映像事業部)
★「-映像資料提供の新しいシステム-についてのご紹介」
(㈱日立製作所ユキビダス・センタ長)
第9回JLA視聴覚資料研究会
2004年2月12日 日本図書館協会
「図書館での映像資料の選択、活用について」
(千葉経済短期大学教授・日本図書館協会ビデオ専門委員)
「映像資料の新しいシステムERIBについて」
(㈱日立製作所ユキビダスプラットフォームグループソリューション統括本部メディアプロセンタ長)
第10回JLA視聴覚資料研究会
2004年9月17日 滋賀県立図書館
「図書館での映像資料の選択、活用について」
(千葉経済短期大学教授・日本図書館協会ビデオ専門委員)
「映像資料の新しいシステムERIBについて」
(㈱日立製作所ユキビダスプラットフォームグループソリューション統括本部メディアプロセンタ長)
第11回JLA視聴覚資料研究会
2005年2月18日 日本図書館協会
「映像資料と著作権」
(戸板女子短期大学・日本図書館協会ビデオ専門委員)
「DVDの選定・装備等の注意点について」
「VOD~ビデオオンデマンドサービスの現状」
(㈱東洋コミニケションズ 常務取締役)
第12JLA視聴覚資料研究会
2005年9月16日 広島県情報プラザ
「映像資料と著作権」
(戸板女子短期大学・日本図書館協会ビデオ専門委員)
「福山市図書館の視聴覚資料の導入と運営」
「図書館向けデジタルコンテンツ配信サービスについて」
「映像資料提供の新しい形~VODサービスの現状と未来」
(㈱東洋コミニケションズ 常務取締役)
第13JLA視聴覚資料研究会
2006年2月17日 日本図書館協会
「図書館におけるICタグの導入の現状」
「笠間市立図書館の映像資料サービスを支えるRF-IDタグ技術」
「より良い映像資料の活用について~権利者側からの提案」
●岩崎陽一(ナクソス・デジタル・ジャパン㈱)
第14回JLA視聴覚資料研究会
2006年9月15日 日本図書館協会
「映像資料と著作権~上映問題について」
「視聴覚資料の受入れにおける許諾確認事務について~岩手県立図書館の移転準備作業における事例~」
「日本映画史データベースの図書館での活用について」
第15回JLA視聴覚資料研究会
2007年2月15日 川口市立中央図書館7階メディアセブン
「合併に伴う視聴覚資料の取り扱い及び業務整理」
●発表者:長谷川清(さいたま市立北浦和図書館)
●発表者:遠間良和(高崎市立図書館・日本図書館協会ビデオ専門委員)
「古代エジプト文明関連DVDについて」
PS.当時、視聴覚資料研究会に参加した人に配布された冊子のため所蔵している図書館は少ないと思われるが群馬県立図書館から要望があり、全15冊寄贈させていただいた。(相互貸借可)当然、日本図書館協会にも所蔵していることは確認済である。
図書館における上映会について
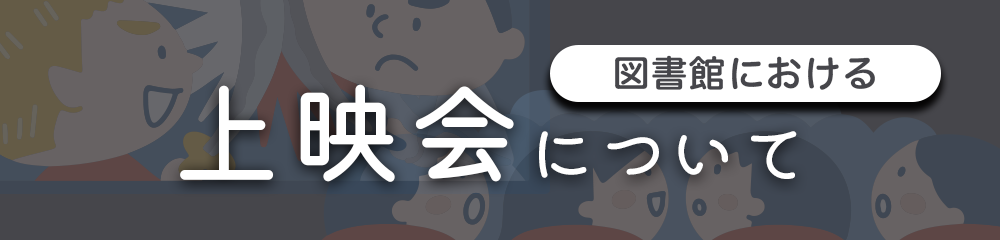
図書館における上映会について①
上映会は著作権法第38条1項により行うことができます。ところがビデオが普及し始めた1980年代後半から、ビデオ業者や映画館の興行主から「最新映画の上映」「無料でたくさん人数を入場させること」に対してクレームが発生するようになりました。
これらをうけ、日本図書館協会のビデオ専門委員会で協議が行われ、自主的な規制として「図書館におけるビデオ映画上映の基本的方針と作品選定の基準について」(1996.9.10)が設けられました。
その後、日本図書館協会と(社)日本映像ソフト協会が協議を行い、上映会のためのガイドラインとなる「合意書」(2001.12.12)が策定されました。
以後はこのガイドラインに沿った運用が行われています。図書館側が上映権付きソフトを求め、上映を行う図書館も増えています。
図書館における上映について②
「図書館におけるビデオ映像上映の基本的方針と作品選定の基準について」の内容 ♦資料「図書館におけるビデオ映画上映の基本的方針と上映作品選定 の基準について」
2. ビデオ頒布後3年以上経過した作品を上映の対象とする(興行上の影響を配慮して)
3. 映画館、レンタルショップでみられなくなった作品を優先
4. 活字資料との関わりを優先
5. 図書館の意思として決定する