監修の遠間が視聴覚担当者時代のエピソードをご紹介。業務に役立つヒントが隠れているかも?
<番外編>みんなの声
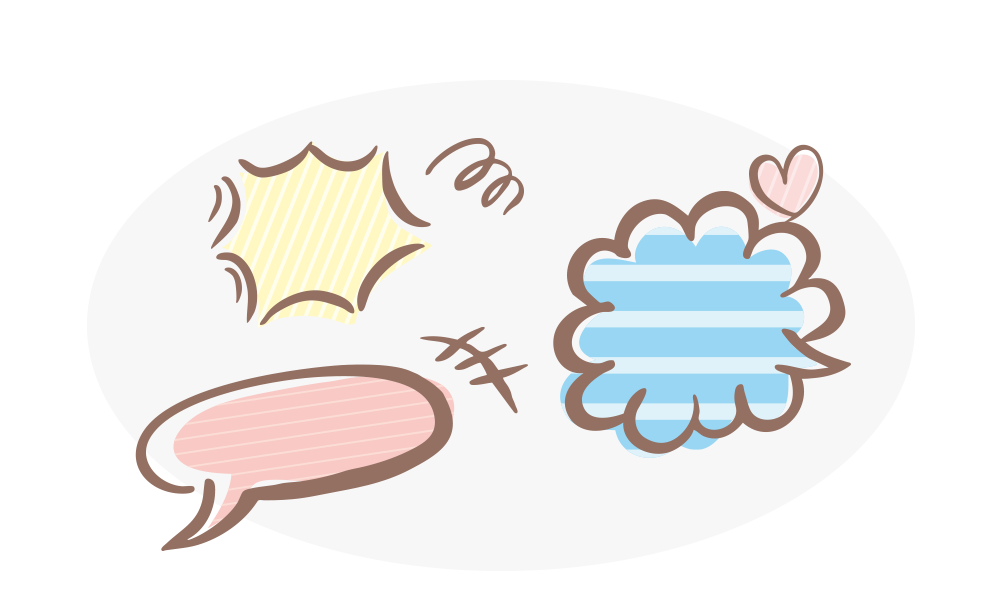
newちょっといい話 ⑨
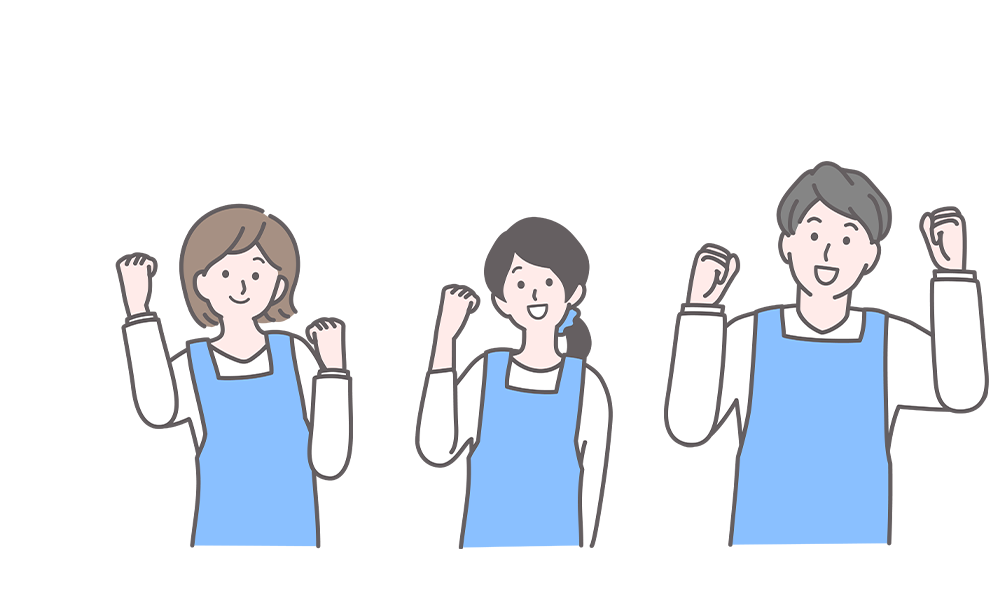
newちょっといい話 ⑧
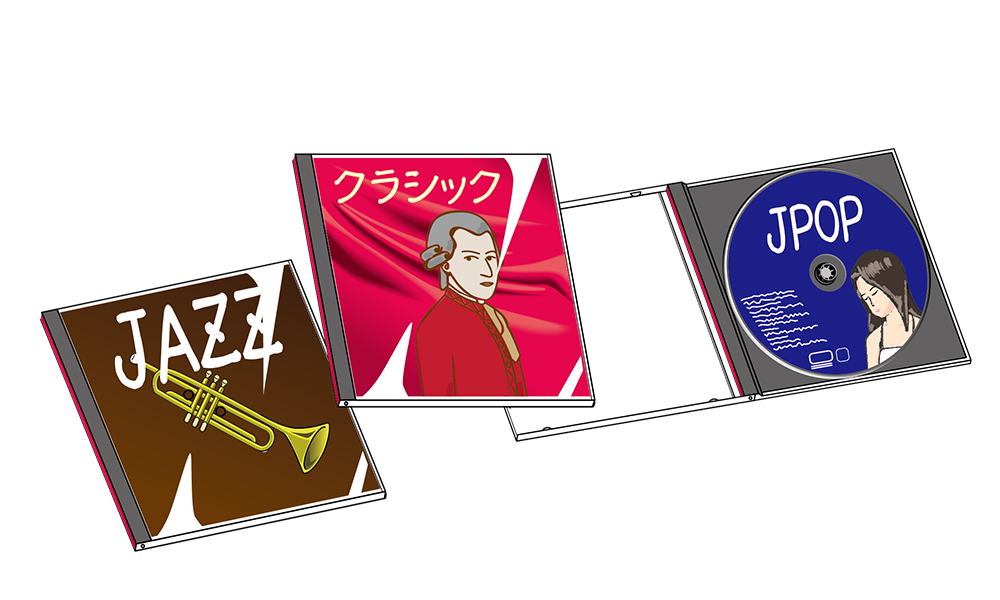
newちょっといい話 ⑦

ちょっといい話 ⑥
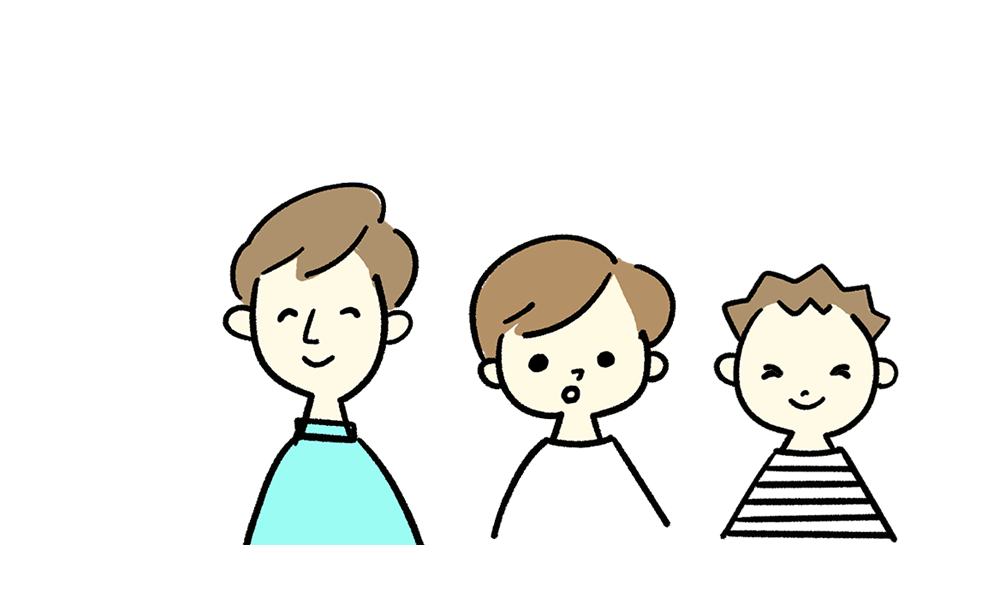
ちょっといい話 ⑤

ちょっといい話 ④
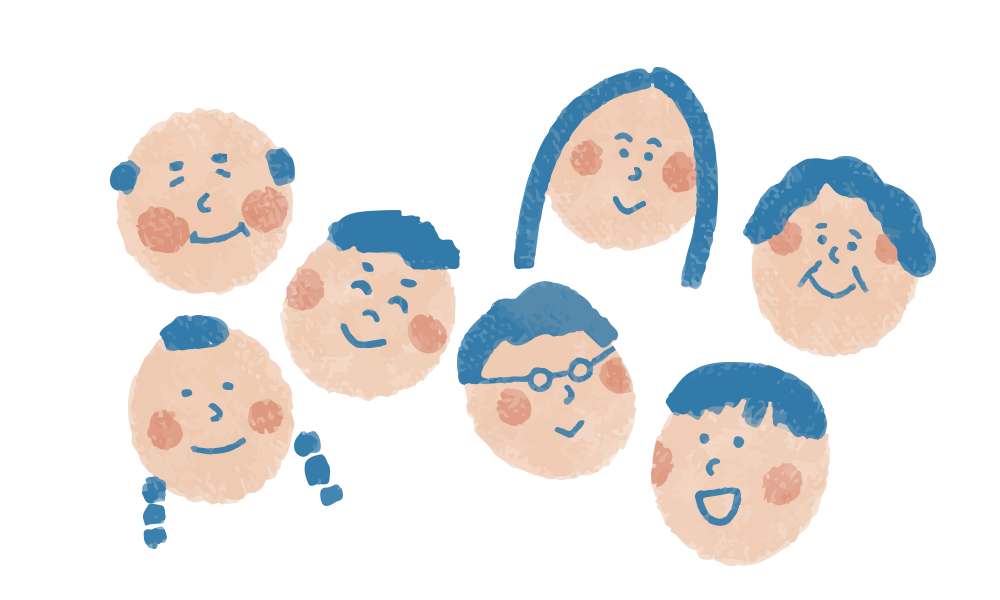
ちょっといい話 ③

ちょっといい話 ②
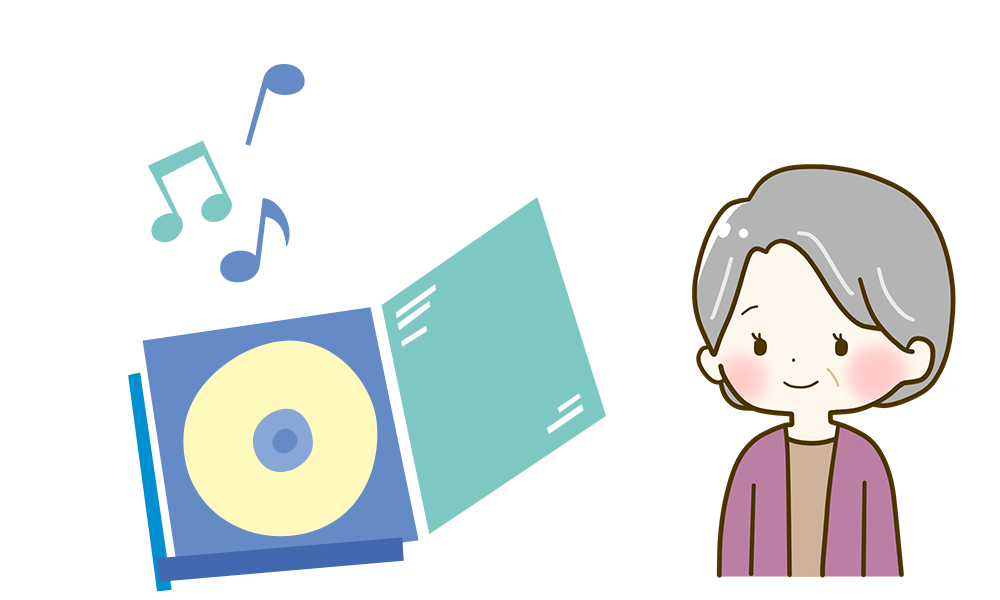
ちょっといい話 ①



