【Q&Aコーナー】仕事に役立つ【Q&A】
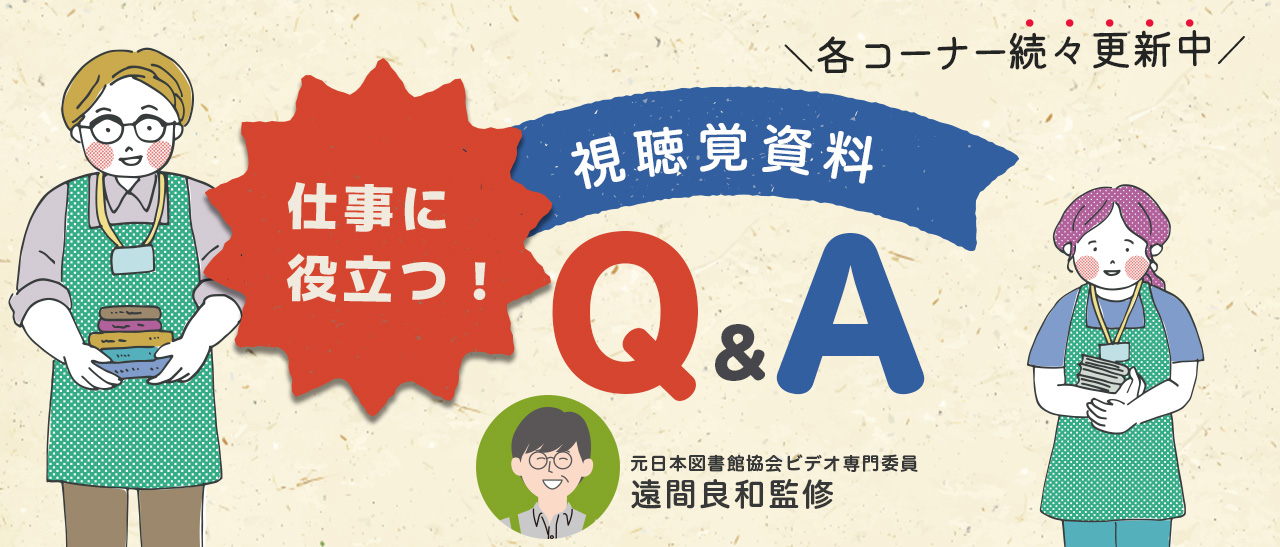

ごあいさつ ~Q&Aの目的と経緯~
図書館における視聴覚資料は、導入当初から担当者が年々代わるがその都度起こる問題点を解決する機関や機会が少ないことなどが課題とされてきました。
また、現在は「日本図書館協会の映像事業部がなくなって図書館問題研究会でも扱わない」「大手販売会社にも聞けないという担当の人たちがいる」など、ますます知識やノウハウを共有する場が少なくなってきています。
そのような状況のなか少しでも問題を解決したり指南出来ればと思い、経験上多かった事例をQ&A方式でお伝えできるようこのサイトに「Q&Aコーナー」を立ち上げました。100%の答えが出なくてもベストな回答を考えていければと思っています。現場を離れて10年経ちますが、視聴覚担当者としての約25年の経験が少しでも現役担当者の方々のお仕事のお役に立てれば幸いです。(遠間良和)
監修:遠間良和
平成元年駒澤大学卒。平成3年図書館情報大学にて司書資格取得。高崎市立図書館視聴覚サービス担当として同館の視聴覚サービスを全国有数のものに育て上げる。平成七年より日本図書館協会ビデオ専門委員会委員として公立図書館を中心に全国で講演会を行う。高崎市立山種記念吉井図書館長など歴任。

弁償・修理
視聴覚資料の弁償は基本的には図書と同じ扱いではあるが映像資料などは高額になることもあり特に注意喚起が必要でしょう。
CDなどは同じ商品がお店にあれば利用者に弁償してもらっても良いが、映像資料などは著作権の関係で図書館側がどうするか決めておく必要があるでしょう。
廃盤や絶版になった資料については弁償対象の資料と同等もしくはそれ以下の指定した資料を購入してもらうとよいでしょう。
CDやDVDの返却の時に、「聴けなかった」とか「観れなかった」など言われることがありますが、そんな時はどうしてますか?
できれば「何曲目ですか?」とか、「映像の何分くらいのところで止まりますか?」など聞いてみましょう。
不良個所があってもそのことを言わずに返却されることがあると、修理が遅くなってしまいます。
元々あったキズは弁償対象ではありませんので、利用者の方にも弁償しなくても大丈夫だと認識していただけるとよいですね。
再生時など不良個所があった際には、気軽に相談していただけるように普段からコミュニケーションをとりやすい窓口にしたいですね。
CDやDVDの裏側(キラキラ面)に傷がついたりすると音が飛んだり映像が止まったりしますが、手で直接触ってつく指紋や汚れでも止まってしまいます。キズがついた資料は確認し、可能であれば修理をしましょう。
修理には研磨機が必要になります。資料は厚さ1.2ミリですが、0.7ミリくらいまでは研磨できます。
それ以上の傷については、研磨できないため修理は不可能です。(0.7ミリより深い傷は記録面に達しているため致命的です。)
キズの予防対策としては、キズ防止クリーナーなどでコーティングするとよいでしょう。赤ちゃんや子どもが口で舐めてしまっても無害の製品がありますのでそういうものを使用しましょう。
<キズの原因と種類>
●挟み傷によるキズ
再生機のトレーにきちんとはめ込まず、少しズレた状態で入れてましうと、挟んでしまったようなキズがつきます。
●放射状のキズ
これはトレーから資料を取り出すときにケースの真ん中(へその部分)突起部分を押さずに強引に取り出すときにせきやすいキズです。ケースによっては親指で押すか、人差し指で押して取り出すと取り出しやすくなっています。(注意書きシールがあるのでうまく活用しましょう)
●円弧状の傷
これはビデオ再生機も特に多かったのですが、再生機内のホコリが一番の原因です。
再生機内のレンズ部分(ピックアップ)に長年のホコリが蓄積し盛り上がった状態で再生すると、そこに資料がこすれ続けることで傷ができてしまいます。こういった利用者に貸出をすると全部傷んで返ってきますので可能であれば特定しておきたいですね。
●その他として
あきらかに利用者によるカッターやコンパスなど鋭利な先の部分で故意にキズをつけられてしまったもの。熱い飲み物や食べ物の下敷にされてしまったもの。夏の暑い時期に車のフロント部分に長時間置かれて変形したもの。
車内ではビニール製のソフトケースに長時間放置するとプチプチと細かい粒子のようなものが付着するとこがありますがそうなると研磨しても修理できません。
映像・録音のこと
(社)日本図書館協会と(社)日本映像ソフト協会とは、公共図書館等における非営利目的かつ無償の映画上映会が、著作権者の利益を損なうことなく、かつ円滑に行われることを目的として、両者間の協議・研究を開始するものとし、この協議・研究の開始に当たって下記のとおり相互に了解する。としたものです。 ♦参考資料「了解事項」
権利者または、メーカーより図書館用に許諾されたビデオ、DVD、Blu-ray等の作品で正規のルートを通って図書館へと提供される映像資料です。
現物配架式(ICタグ・タトルテープ)有、なし(※ない場合は紛失のリスクあり)、交換式、ダミーケース式、クイックケース式、オーダープレート式など様々な方式があるでしょうが資料が増えるにつれ資料の保存スペースが必要となったり貸出時の確認など手間が増えたりします。
そのほか
ユネスコ国際音声視聴覚アーカイブ協会(IASA)、オーストラリア国立フィルム&サウンドアーカイブ協会(NFSA)などが「磁気テープの音声や映像は2025年までにデジタル化しなければ永遠に失われてしまう」と警鐘を鳴らしています。
アナログで記録されたビデオテープやカセットテープなどの媒体は 劣化が進み徐々に再生出来なくなってしまう恐れがあります。
さらに再生機器の減少によりご自宅にある家族との貴重な思い出を記録したテープなどは個人でダビングするか民間業者に委託することになります。
図書館にもアナログ媒体のビデオテープやカセットテープなどを所有していますが利用が少なくなったことで書庫で保管していることでしょう。備品で購入したため簡単には除籍するわけにはいきません。二度と手に入らない貴重な記録として後世に残す手立てを考えていくことが図書館の使命であることを忘れないようにしましょう。
最近のレコードプレーヤーの復活やラジカセの再販によるレトロブームに象徴されるように、今後、ビデオデッキが再発売された時のためになんとか保管してほしいものです。
図書館法第17条には「公立図書館」は入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない」とあり、いわゆる「図書館資料の原則」に基づいているからです。
B-D-S(ブック ディテクション システム)やセキュリティゲートと呼ばれ磁気式と電波式があります。図書館資料に貼付することで貸出手続きをせずに館外に出ようとするとゲートが反応してブザーが鳴ります。
図書館に所蔵している資料ならば予約可能としている図書館は多いでしょうが所蔵点数が少ないことや予約多数の場合提供できる時間がかかることを伝える必要があるでしょう。また、リクエストに関しては著作権の関係で高額であったり、絶版・廃盤により購入できない作品や他館から借りることも難しいため、あくまでも参考程度として受付をすることを利用者に伝えるかあるいは、購入できないと伝える
CDについては貸出しても大丈夫です。但し、自館で登録や装備をしなくてはなりません。
DVDについては貸出はできません。ビデオについても現在は利用が少なくなっていることを踏まえて、寄贈はお断りした方が賢明です。
個人メールでのお問合せも大歓迎です!
\ 図書館のお仕事に携わる方ならどなたでも! /
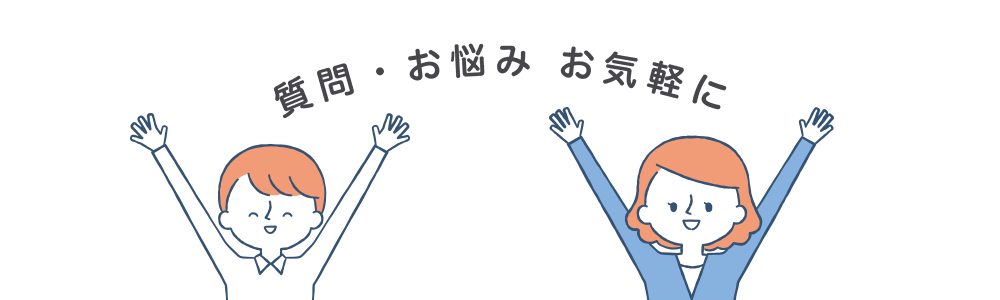
図書館の視聴覚に長年携わってきた先輩方がお答えする質問BOXです。
Q&Aに載っていないお悩みやご相談をお気軽にどうぞ!
(※必要事項をご記入の上、送信ボタンを押してください。)







